2024年大晦日、義父が逝去しました。9月に風邪をこじらせ肺炎になってから寝たきりの介護をしていましたが次第に食べることが出来なくなり、大晦日の19時ごろ家族に看取られ逝去しました。
私はこれまで、多くの高齢者施設(高額なところから、年金でも入れるようなところまで)に訪問施術に行った経験から、もし自分が介護を受けるような状態になったときは、施設介護よりも在宅介護と思っていました。でもそれは、施設介護しか知らない状態で思っていたことだったので、今回実際に在宅介護を経験(ほとんど家内がしてましたが・・・)したことで感じた、在宅介護における家族の役割や、私が感じた在宅介護のメリット・デメリットなどをお伝えしたいと思います。
家族の条件
在宅介護をする上で一番重要なことは、同居していることです。当たり前ですが、身体の状態が悪くなるにつれて不安定になり、昼夜問わず対処しないといけないからです。
そもそも、私も義父母とは別に暮らしていました。5、6年ほど前に母が加齢黄斑変性という眼病であることが判明。その頃から、父母ともに認知症の傾向もあり近い将来、必ず自活できなくなることが予測されたので、試験的に私の家で同居をしてみました。が、やっぱり住み慣れた家がいいとのことで上手くいきませんでした。それからなんやかんやで、1年ほど前から私たちが押しかけ義父母の在宅介護がはじまりました。
2番目に重要なことは、姉弟の協力です。はっきり言って一人では無理です。今回も家内一人では成り立たなかったと思います。
事実、息を引き取った日の前日から家内は発熱し寝込んでいて、私が家内を病院に連れて行っている間に急変し、戻って来るまで何とか引き留めてくれたのが弟夫婦と娘で、そのお陰で、家内も私もそして息子(孫)も死に目に間に合うことができました。
当然、訪問看護サービスは受けていましたが、最終段階に入ると息がなくなったら連絡くださいとなるので、最後のときは家族に委ねられます。なので、最後は家族に看取られたいと思う方にはおすすめです。
住居環境
介護=バリアフリーと思われる方が多いかもしれませんが、我が家は築30年以上の3階建てで、バリアフリーとは程遠く住宅の改修といえば階段、風呂場、トイレに手すりを付けたぐらいです。
また、入浴は訪問入浴サービスを受けることで、2階の居間でも入れました。そのお陰で亡くなる3日前、食事も取れないやせ細った体の状態でも、気持ちよさそうな顔で湯船に浸かり急変することもありませんでした。

家族がすること
では、実際に家族がすることを紹介します。
体位変換
体力が低下してくると血流が悪くなります。体力が低下してくると自分で寝返りができなくなり、体圧がかかっているところに褥瘡ができます。それを防ぐために介護用のベットが必要不可欠となり、定期的に家族が体位を変換しなければなりません。
おむつ交換
寝たきりになると、排尿は膀胱から直接管を介して袋に出すケースが多いようです。いわゆるバルーンというやつです。バルーンの臭いはほとんどしませんが、排便は別です。
食べれる量にもよりますが時折り排便があり、その都度おむつの交換が必要です。そして、排便は臭いがします。それもかなりきつい臭いが・・・・
また、食べることが出来なくなって、いよいよ最後になると黒い宿便のようなものが大量に出ると思っておいてください。なので、我が家では、臭い取りに空気清浄のような機械は購入しました。
水分摂取
食べれなくなってくると点滴に補給を頼るしかありません。ここで家族にはある選択がせままれます。それは、点滴をどこまでするのか?胃瘻(いろう)までするのか?ということです。
在宅にかかわらず、施設でも胃瘻をしている方はいます。そんな方たちを見ていたこともあって胃瘻までしなくても・・・と私は思っていました。それは、姉弟とも同じ意見でした。なるべく苦しまず自然な形で、というのが全員の想いだったので、一番自然な形で最後を迎えることが出来たと思います。
バイタルチェック
バイタルチェックとは、体温、血圧、脈拍、血中酸素濃度などで、この他にも食事や水分の摂取量、排便の有無などを定期的に記録することです。

吸引
人の体の7割は水分だといわれています。なので、口から水分が取れなくなっても点滴で水分を入れます。
でも、体の機能が低下してさらに代謝が悪くなると、手足が浮腫んできます。そして、痰が喉を塞ぎ呼吸を困難にさせます。
吸引とは、機械でその痰を取除く作業です。
素人でも出来ますが、吸引される方は苦しいので嫌がります。でも、半ば無理やりでもしないと、息ができなくなりそのまま亡くなる方も・・・・なので、介護する側の覚悟が試される処置です。でも安心してください。もし上手く取れきれなくても、訪問看護に連絡すれば夜中でも駆けつけてくれるので、家も大変お世話にありがたかったです。
在宅介護のメリット・デメリット
在宅介護にはメリットとデメリットがあり、家族や介護者の状況に応じて適切な選択をする必要があります。以下に詳しく解説します。
在宅介護のメリット
家庭的な環境で生活できる
自宅という慣れ親しんだ環境で生活を続けられるため、心理的安定やストレス軽減につながると考えられます。実際に余命宣告受けてからは、状態がわるくなっても持ち直し、主治医も数値的には理解できないと驚いていました。
家族との時間を共有できる
施設介護と異なり、いつでも家族が立ち寄ることが出来るので、家族と触れ合う時間が増え、本人の安心感や生きがいにつながります。実際に義父も、反応が悪い日でもひ孫の顔を見せると、いつもあやす様なそぶりを見せたりして、最後まで誰が来たのか分っているようでした。
個別に対応しやすい
施設のような集団生活ではなく、個々のニーズに合わせた介護ができるため、柔軟な対応が可能です。
費用を抑えやすい
施設介護は費用が高額になりがちですが、在宅介護の場合は介護保険サービスを上手に利用することで、比較的費用を抑えられる場合があります。施設では長生きさせる(息をさせる)ことが目的になっているように思います。
リハビリや生活訓練がしやすい
残念ながら、義父の場合は叶いませんでしたが、施設では寝かされていることが多いようですが、生活の場がそのままリハビリや生活訓練の場になるため、日常生活に密着したケアが行えます。
在宅介護のデメリット
家族の負担が大きい
訪問看護師が帰った後とか、夜遅くに状態が悪くなることが多いと、介護者は身体的・精神的に大きな負担を強いられることが多く、介護疲れやうつ状態になるリスクがあります。
24時間対応が必要になることもある
夜間の対応や急な体調変化に備える必要があり、介護者の睡眠や休息が十分に取れないことがあります。
医療・看護の対応が難しい
自宅では医療設備が整っていないため、医療的なケアが必要な場合は訪問看護や訪問医療を依頼する必要があります。家の場合は、在宅を始めたすぐに口腔内に腫瘍があるのがわかりましたが、検査や治療に耐えるだけの体力がないと家族で相談し判断しました。したがって、医療的な処置は、点滴と酸素吸入機で酸素を送るというもので、積極的な治療は行わず、ターミナルケアを中心にするという方針でスタートしました。

住宅の改修が必要になる場合がある
バリアフリー化や手すりの設置、介護ベッドの導入など、住宅改修に費用と時間がかかることがあります。
社会的孤立のリスク
介護を担う家族は外出や仕事を制限されることが多く、社会とのつながりが希薄になる可能性があります。
介護者の専門知識不足
家族だけで介護を行う場合、認知症ケアや身体介護の専門知識が不足し、適切な対応が難しいことがあります。訪問看護のサービスが入っていると質問や相談をすることが出来るので心強いです。
在宅介護を成功させるための5つのポイント
- 公的サービスの積極的な利用
訪問介護、訪問看護、デイサービス、ショートステイなどを利用し、家族の負担を軽減しましょう。 - 家族間での役割分担
一人に負担が集中しないよう、家族間で役割を分担することが重要です。 - 介護者の休息を確保
介護者自身の心身の健康を維持するため、定期的に休息を取ることが大切です。 - 地域の支援を活用
地域包括支援センターや介護相談窓口などを活用し、情報や支援を受けましょう。
まとめ
在宅介護は家庭的な環境で本人を支えるメリットがある一方で、期間が長くなればなるほど家族の負担が大きくなるデメリットもあります。
義父の場合は、肺炎で体力が低下したことが在宅介護に踏み切るきっかけとなりました。在宅介護を始めた当初は、3ヶ月で亡くなるとは思っていませんでした。
私の両親はすでに他界していますが、父は、入浴中に意識がなくなりその翌日に、母は10年間透析を受けながらも自律した生活を続け、朝、透析に迎えに来たのに反応がないことで消防に連絡。自宅のベット横で倒れ亡くなっているのを発見されたそうです。
二人とも急死でしたが、義父は家族みんなに看取られ最後は苦しむ様子もなく静かにひきを引き取りました。不慣れなことばかりで手探り状態はじめた在宅介護でしたが、介護をされる側する側、両方にとって気持ちを整理するのに必要な準備期間であったように感じました。
お父ちゃん、ありがとう!お疲れさまでした!


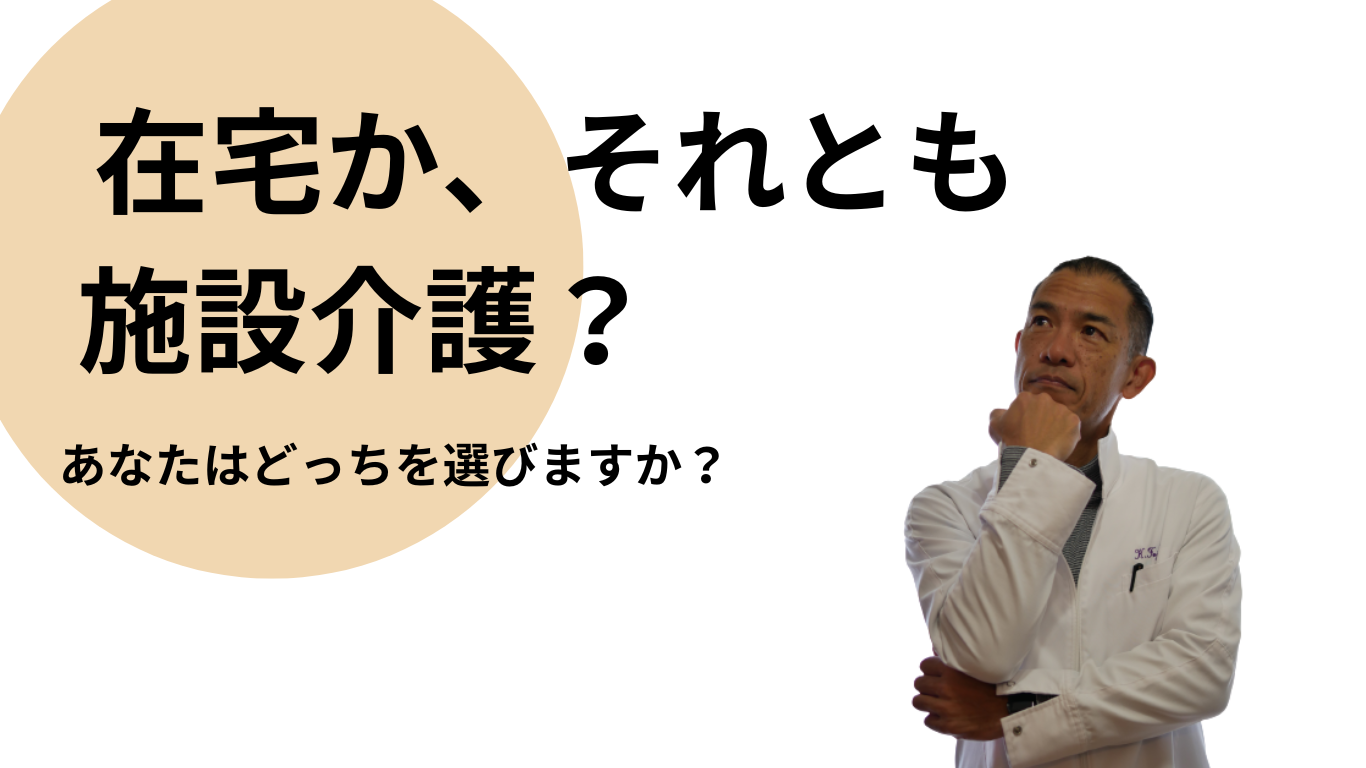


コメント